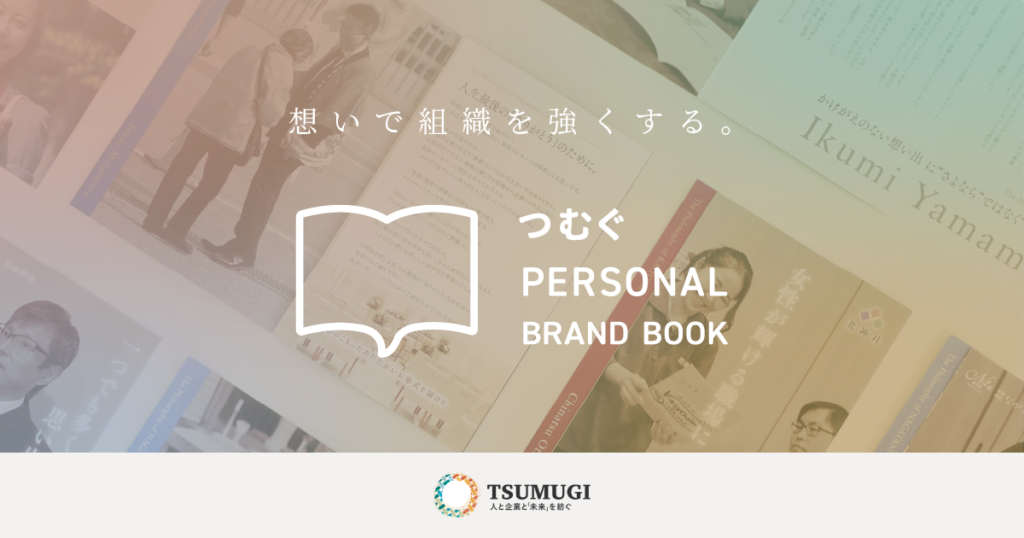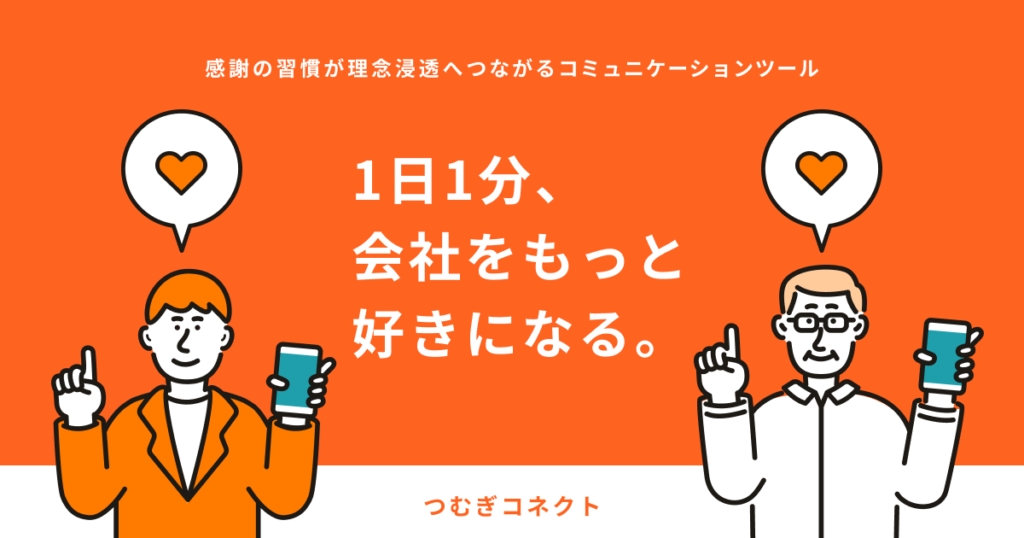人手不足が深刻な産業廃棄物業界では、「採用しても定着しない」「やる気が続かない」といった悩みが経営層・現場双方で顕在化しています。特に若手の離職は大きな課題となっているケースが多いです。
「業界がら若手いなくなってしまうのはしょうがない」と、考えたことのある経営者様は多いのではないでしょうか?
しかしその課題は、もしかすると若手の問題なのではなく「働く意味を感じづらい職場」になっていることが本質かもしれません。
待遇改善だけでは限界がある今、会社への共感や誇り、自主的な貢献意欲──つまり“エンゲージメント”が、定着率や生産性に直結する時代です。
本記事では、産廃業界におけるエンゲージメント向上の必要性、実践できる施策、成功事例を紹介します。
“やる気”や“忠誠心”とは違う。「エンゲージメント」の正体
エンゲージメントとは、会社や仕事、そして共に働く仲間に対して自発的に貢献したいという意欲のことを指します。単なる「やる気」や「満足感」とは異なり、もっと内面から湧き上がるような“共感”や“誇り”に近い概念です。
たとえば、「この会社のビジョンに共感している」「この仲間とだから頑張れる」「この仕事が社会に役立っていると感じる」といった感覚。それがエンゲージメントの土台です。エンゲージメントが高い人は、言われなくても動き、困っている同僚を助けたり、自分の役割を超えて価値を生み出そうとしたりします。
しかし、この言葉は他の人事・マネジメント用語と混同されやすいため、あらためて違いを整理しておきましょう。
混同されがちな概念との違い
-
- モチベーション
→ 一時的・外的な刺激によって湧き上がる「やる気」のこと。たとえば昇給や賞与、達成感などがきっかけになるものです。ただしこれは継続性に乏しく、上がったと思えばすぐに下がることもあります。 - ロイヤルティ
→ 会社に対する「忠誠心」や「義理人情」に近いものです。たとえば「長年お世話になってきたから辞めづらい」といった感覚がロイヤルティに該当しますが、必ずしも主体的な貢献意欲とは一致しません。 - 従業員満足(ES:Employee Satisfaction)
→ 主に「給与」「福利厚生」「職場の快適さ」といった、外的条件への満足度を指します。たとえば「休みが取りやすい」「オフィスがきれい」などはESを高めますが、それだけではエンゲージメントにはつながらないこともあります。
- モチベーション
これらと比較すると、エンゲージメントは“心の深いところ”から湧き上がる共感や使命感に近いことがわかります。特に産業廃棄物業界のように、仕事の意義が外からは見えにくく、社会的評価も高くない現場では、この“内なる納得”が働きがいの根幹となります。
だからこそ、待遇や制度の整備だけでなく、「自分の仕事には価値がある」「仲間と一緒に頑張りたい」と思える状態をつくることが、これからの組織には求められているのです。
なぜ産廃業界は“エンゲージメント”が命綱になるのか?
産業廃棄物業界は、社会を下支えする重要なインフラ産業でありながら、その貢献が一般には見えにくく、評価されづらい現実があります。「誰かがやらなければならない仕事」である一方で、「誰にでもできる仕事」と誤解されがちで、働く側が誇りを持ちにくい構造にあります。
また、現場は広範囲に分散しており、支社や現場単位での孤立感が生まれやすく、会社全体の一体感や仲間意識を育むのが難しいという特徴もあります。こうした環境下では、働く意味や仲間とのつながりが希薄になりがちで、やる気や定着率の低下につながってしまいます。

さらに、業務の性質上、安全面や品質対応、顧客とのやりとりにおいては、現場スタッフ一人ひとりの判断力や自律的な行動が企業の信頼や成長を大きく左右します。ただ“言われたことをこなす”だけではなく、「自分がこの会社の価値をつくっている」という意識を持って動いてもらう必要があるのです。
だからこそこの業界においては、給与や待遇だけでは補いきれない内面的な納得感=エンゲージメントの醸成が不可欠です。社員一人ひとりが誇りと責任感を持って働ける状態をつくることが、企業全体の持続可能な成長を支えるカギとなるのです。
社員の心を動かす、エンゲージメントの3つの土台
エンゲージメントは、単に個人の気持ちに任せるものではありません。企業として、また現場の上司として、「どうすれば高まるか」という設計と実践が重要になります。特に大切なのが、以下の3つの要素です。
① 理念・ビジョンの共有と対話
エンゲージメントの土台には、「自分の仕事は何のためにあるのか」という納得感が必要です。たとえば、「なぜこの会社が存在するのか」「どんな未来を目指しているのか」「私たちの仕事は社会にどう役立っているのか」といった問いに対して、答えが見える状態にあること。
理念やビジョンは、社長だけが語るものではなく、現場と対話を通じて“自分ごと”に落とし込むプロセスが欠かせません。
② フィードバックと承認
人は誰かに「見てもらえている」「認めてもらえている」と感じることで、初めて主体的に動こうとします。「ありがとう」「助かったよ」という一言が、何よりも働く意欲を支えます。
また、努力や工夫が認識されず、ただ“当然の仕事”として流される環境では、やがて無力感や不満が募ってしまいます。小さな成果に光を当てることが、エンゲージメントの火種になります。
③ 働きやすさと成長機会
物理的・心理的な働きやすさも、長く安心して働くためには不可欠です。たとえば「道具や制服が扱いやすい」「相談できる上司がいる」「自分のスキルを伸ばせる機会がある」といった要素は、現場スタッフにとっては大きな安心感や前向きな姿勢につながります。
会社が社員の成長を応援する姿勢を示すことで、社員は「自分はここで大切にされている」と感じ、自ら貢献したいという気持ちを育むのです。

明日からできる!現場が変わる“エンゲージメント10の工夫”
エンゲージメントを高める取り組みは、特別な予算や制度を必要とするものばかりではありません。日々の現場のなかでも、少しの工夫で実践できることがたくさんあります。以下に紹介する10の施策は、すぐにでも取り入れられるものばかりです。
朝礼や終礼での理念共有(週1回だけでも)
理念やビジョンを短い言葉で伝えるだけでも、「自分たちは何のために働いているのか」を確認できます。
月1回の「1on1面談」で小さな悩みを拾う
形式ばらずに話を聴く時間をつくることで、本人も気づいていない不安やモヤモヤが見えてきます。
「ありがとうカード」や「称賛制度」で日々の行動を評価
小さな貢献にも感謝を伝える文化が、仲間同士の信頼やモチベーションを育みます。
社員インタビューや掲示で仲間の価値を見える化
「誰がどんな思いで働いているか」を社内に紹介することで、相互理解が深まります。
入社記念日・誕生日の声かけや手書きメッセージ
些細なことでも“覚えていてくれた”という実感が、信頼関係の構築に寄与します。
現場提案制度(改善案・声を拾い実行)
現場の声を形にすることで、社員に「自分の声が届く」という実感を持ってもらえます。
外部研修・社内勉強会でスキル向上
学びの機会は、働くことの意味や将来像を描くうえで大きな支えとなります。
社長メッセージ動画/手紙でトップの思いを伝える
トップの言葉が直接届くことで、「自分たちは大事にされている」と実感できます。
制服・道具の改善に社員の声を反映
日常業務に関わるツールの改善は、「仕事のやりやすさ」と「気持ちよさ」の両面に効果的です。
定期アンケートとフィードバックで対話ループをつくる
一方通行で終わらせず、声を聴き、返し、改善につなげるサイクルが信頼を築きます。
これらの施策はすべて、「現場でできる・継続できる・小さく始められる」ことを前提に設計されています。最初から完璧を目指す必要はありません。できることから一つずつ、小さな“関係づくり”の習慣を積み重ねることが、エンゲージメント向上の第一歩です。
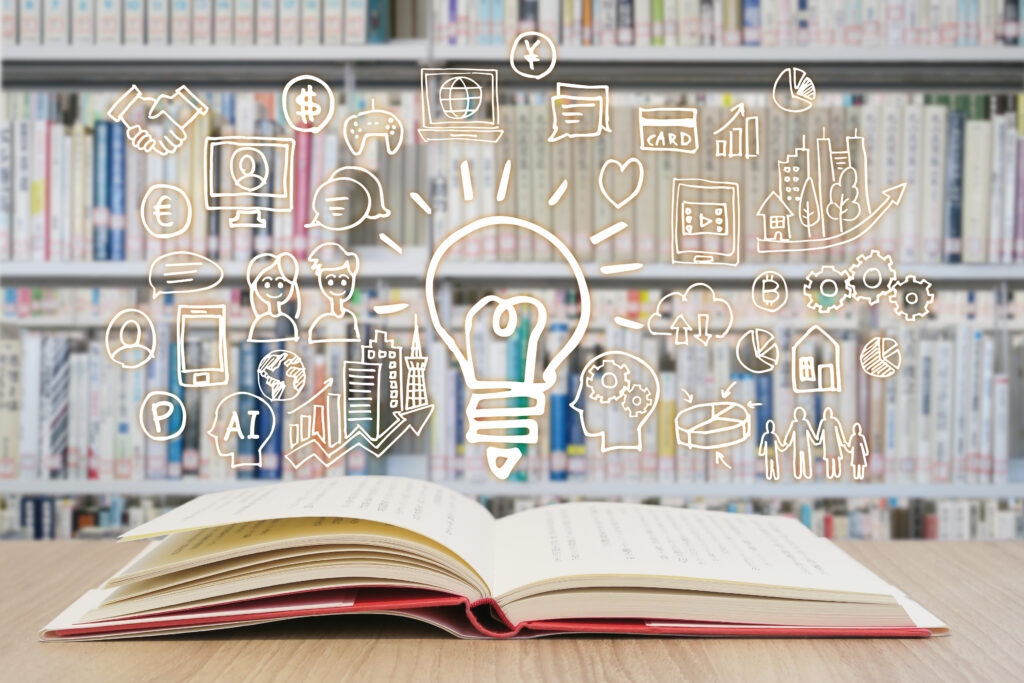
「時間がない」「理解されない」現場の声に答えます
Q. 忙しくて取り組む時間がありません…?
A. 朝礼5分の声かけや、週1回のミニ1on1など、まずは“小さな仕組み”から始めましょう。
Q. ベテラン社員が「そんなの甘やかしだ」と反対する場合は?
A. 「安心感が仕事の質を上げる」ことを丁寧に共有し、巻き込む姿勢が重要です。
Q. 小規模でもやれることはありますか?
A. 手書きメッセージや相談タイムなど、コストゼロでもできる施策は多数あります。
「何から始めればいい?」その第一歩を一緒に考えます
もし「どこから手をつけていいかわからない」「どんな制度がいいのか?」と感じられた場合は、ぜひお問い合わせをいただければと思います。中小企業の人事領域に対し豊富な知見を持つコンサルタントと、30分間無料でご相談が可能です。
エンゲージメント向上を図るためには、理念・ビジョンの共有と対話が重要となります。そして様々な施策を掛け合わせることで始めて実現することができるのです。
つむぎではエンゲージメント向上を図るための一施策として、パーソナルブランドブックというサービスを提供しております。社員一人ひとりにインタビューをし、パンフレットを制作。働く想いや成長を可視化するというサービスです。
ご興味がございましたらぜひページをご確認いただければと思います。
エンゲージメント向上に関係する記事は下記にもまとめています。この機会にぜひご一読ください。
8月4日には産廃業界に特化した採用戦略、そしてその成功事例を紹介する無料のオンラインセミナーを開催いたします。ゲストは東京都八王子市で活躍するまごころ清掃社様です。時間は10時から。ぜひご参加ください。
「ありがとう」から始まる、“働きがい”ある現場づくり
エンゲージメントは“待遇”ではなく“関係性”と“共感”で生まれます。
小さな仕組みを現場と一緒に育てることで、「働きがいのある会社」は実現可能です。まずは、社員の声を聴き、「ありがとう」を伝えることから始めてみましょう。