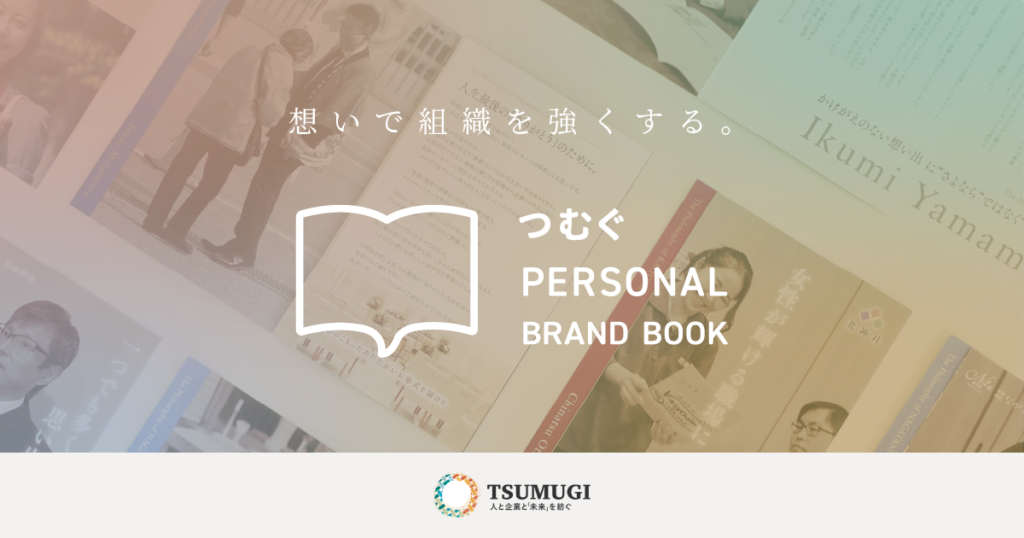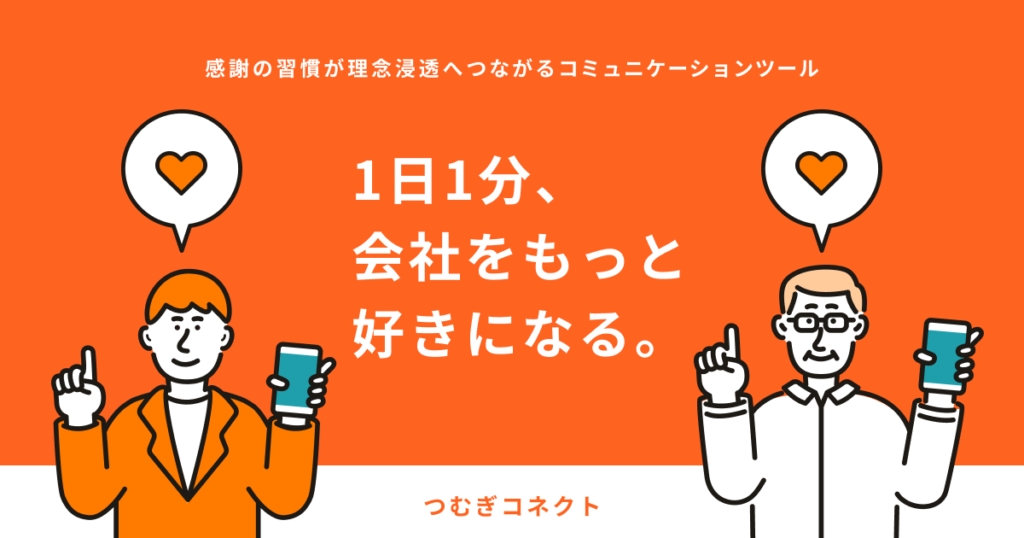つむぎがご提供するサービスを1つずつ紹介するつむぎサービス大辞典。今回ご紹介するのは「採用面接プログラム」です。
「採用面接プログラム」は採用面接時間の質をより良いものにすることで選考希望率を高め、面接離脱率を下げることで、より良い面接合格者の選定や入社後のオンボーディング、離職防止に貢献するサービスです。
今回は採用面接プログラムを担当する吉田有輝に、採用面接プログラムの概要から進め方に加えて、お客様からいただいた声なども伺いました。「面接を辞退されることが多い」「入社してもすぐ人が辞めてしまう」という課題を抱えていらっしゃる方は、ぜひ最後までお読みください!
面接の時間をより良くするため、応募から内定承諾までをサポートする 「採用面接プログラム」
採用面接プログラムは、採用における応募から内定承諾までをサポートするサービスです。
採用4Pとよばれるフレームワークを用いて、企業の魅力を伝える採用ピッチ資料を制作。採用担当者に伴走し、企業の良さを適切に伝え、求職者に、より興味を持ってもらうための採用面接時間を醸成するサポートをしていきます。

支援は、まず採用全体の課題感をヒアリングするところからスタートします。その上で現在の採用フローを確認します。その後、求職者のペルソナを構築し、企業を形成する要素の可視化作業を行っていきます。求職者の方にお伝えするストーリーテリングをした後に採用ピッチ資料の制作を進めていきます。
採用ピッチ資料の制作では、採用4Pの要素である理念・目的、会社・事業、人材・風土、待遇に分けて企業の魅力を言語化します。
そしてその言語化された魅力をもとに、応募から面接までにどういうストーリーを構築できれば候補者を惹きつけられるか、さらに面接でどういった質問をすれば候補者を適切に評価できるか?を考え、評価シートを作り上げていくのです。
一言でいえばこの採用面接プログラムは「面接時間をより良いものにし、求職者の入社意欲を高める」ということができるでしょう。
第一志望群で終わらないために
採用面接プログラムは現代の採用活動において大きな意味を持つサービスです。採用面接プログラムは、採用活動において大きく二つの効果を持ちます。
まず自社が求職者から選ばれる企業になれるというという効果です。現代の採用活動、特に新卒採用において、求職者は企業へ興味を抱いておらず、また企業の詳細も理解していない状態で採用応募をしているケースが多くあります。

「本命に落ちてしまうかもしれないから、とりあえず何社か応募出しておこう」というイメージです。
そのため現在は“第一志望”、“第二志望”という言葉だけではなく、第一志望群、第二志望群という言葉が生まれています。
それぞれには、本来の志望企業とその企業と魅力を感じている数社が含まれています。
例えば第一志望群であれば、第一志望である企業と、その企業と同じくらい魅力を感じている数社が含まれます。
つまり現代の採用活動において求職者は第一志望の中でも、さらにどの企業がいいか、絶えず判断を重ねているのです。こうした背景から企業側には「こちらが出す内定数はKPIに達しているのに、内定承諾者はKPIを下回ってしまった」、「面接の通過を伝えた際、求職者に面接を辞退されてしまった」という課題が生まれてきています。
特に一件の応募が大切な中小企業やベンチャー企業にとっては深刻なものといえるでしょう。
この問題は日本において企業数が増加しているからこそ発生しています。
求職者は膨大な企業情報を処理する手間を省くため、概要を見ただけで応募を決断。一方で企業はライバルが増加する中で人材を確保するため、情報量を増加させます。
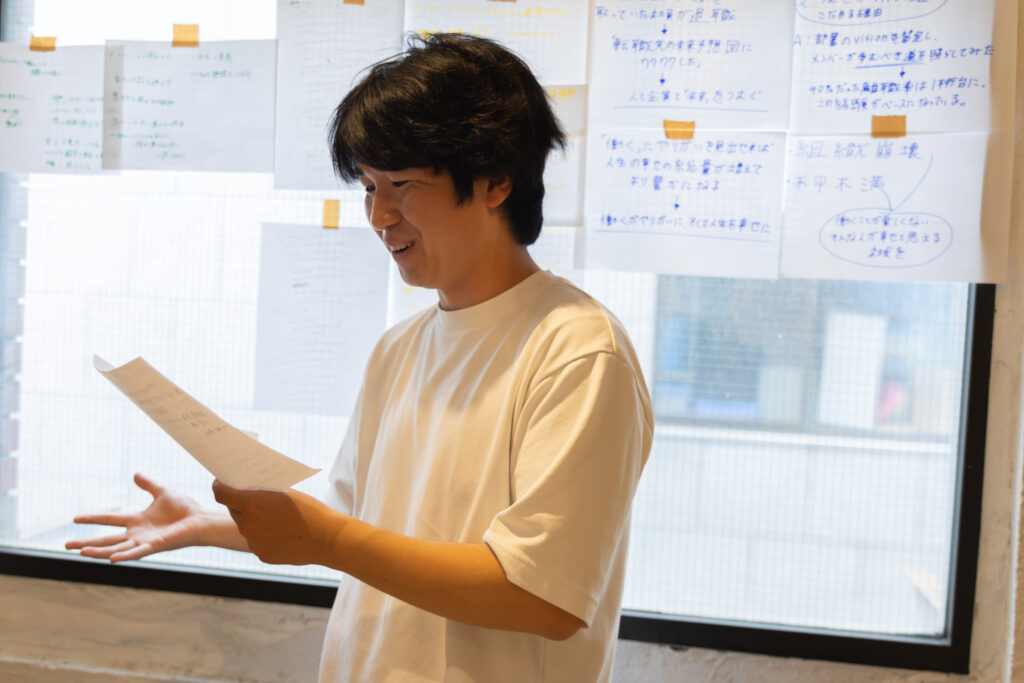
その結果ただでさえ膨大な量の情報がさらに増え、判断材料を見えにくくする、という悪循環に陥ってしまっているのです。
こうした課題を解決するためには、まず、応募の段階で求職者に第一志望郡の中から自社を第一候補として選んでもらうための情報発信を組み立てることが重要です。
具体的には自社の魅力を整理し、採用ピッチ資料を通して求職者が自社に興味を持つようなストーリーテリングをしていく必要があります。
自社の魅力をしっかりと伝えることできれば、求職者は自社に抱く期待感が向上させることでしょう。さらに入社後のやるべきことや、成長サイクルがはっきりしていれば入社後の不安は低減します。
その結果、第一志望群にいる他社との印象に差がつき、求職者は自社を第一志望と捉えるようになるのです。
次に大きな効果は自社で活躍する可能性が高い人材を獲得できるようになるということです。
面接の前段階で企業の魅力を伝えてられていれば、その後の面接を、求職者の人柄を知るための場にすることができます。

そのため企業は、自社の風土と相性が良くこれから活躍してくれそうな人材、一言で言えば自社にマッチした人材を求職者の中から選べるようになるのです。
入社後のオンボーディングの効率化やエンゲージメント強化による離職防止といった効果が得られるでしょう
また自社にマッチした人材の獲得は上記だけに留まりません。
その後の獲得した人材は当然、企業活動を通して売上を生み出していきます。そのため、ある意味では採用面接プログラムは業績の向上をはじめとした企業活動全般にも好影響を与えると考えられるのです。
採用4Pに沿って企業の魅力を言語化し、求職者の本質に迫れる質問を構築。面接をより良い時間にする
最終的に目指すのは面接の時間を、求職者が「ここで働きたい!」とワクワクするための時間とすることです。
また企業側の視点では、求職者本来の人柄を知り、共に未来を歩む仲間を見つけるための時間とすることを目指します。
面接をより良い時間とするために最も肝となるのは、意外にも採用4Pと呼ばれるフレームワークに沿った採用ピッチ資料作りです。
採用4Pは人事戦略で用いられるフレームワークの一つで、「なぜ企業が存在するのか」というフィロソフィー「なぜこの事業をやるのか」というプロフェッション、「どんなメンバーや社内の雰囲気があるのか」というピープル、「どんな福利厚生や社内イベントがあるのか」などのプリビレッジの4つに整理します。
企業の特徴を採用4Pに整理することは、採用ピッチ資料以上の意味を持ちます。実は一説には、一連の採用活動において企業は自社の魅力を30%~40%しか伝えられていないといわれています。
その結果、面接受ける前に候補者が検索した際に閲覧できる情報と面接後時に候補者が伝えられる情報に差がないという状況が生まれてしまっているのです。これでは双方時間をとって面接を行う意味がありません。

面接を意味のある時間とするためには、企業側がまず自社の魅力を把握し発信する必要があります。つまり採用4Pに沿って自社の魅力を言語化することは、採用活動全体を効率化させるための土台ともいえるのです。
こうして企業の情報を伝える土壌が整った後は、面接時の質問案を構築していきます。採用ピッチ資料において自社の魅力を伝えたことで、面接を候補者の人柄を知るための時間として使えるようになるのです。
「どういう質問すれば、どういう要素がわかるのか」というアセスメントと呼ばれるシートを用い、構築したペルソナに合わせた質問内容を考えていきます。
こうすることで「Aという要素においてはこの基準以上」、「Bという要素においてはここまでの資質が欲しい」というような働く上で求められる能力を、定量的に把握することが可能となります。そして企業は安定して自社にマッチした人材を獲得できるようになるのです。
「人」だからこそできる、求職者の本音に迫る面接を
採用活動において面接は「人」にしかできないことだと考えています。
質問や点数づけだけであればAIにもできるかもしれません。しかしそれではただ受け答えに過ぎません。求職者から得られる情報は、面接のために作られた内容となるでしょう。

求職者の本来の人柄に触れ、そして本音を引き出すには、求職者に寄り添い心を溶かすようなアプローチが必要となります。それはきっと、心があり相手を思いやることのできる人間にしかできないことだと私は考えています。
採用面接プログラムを通じて、少しでも多くの企業様の採用課題解決に貢献したいと思っています。一緒に御社ならではの採用ストーリーを形にしていきましょう。