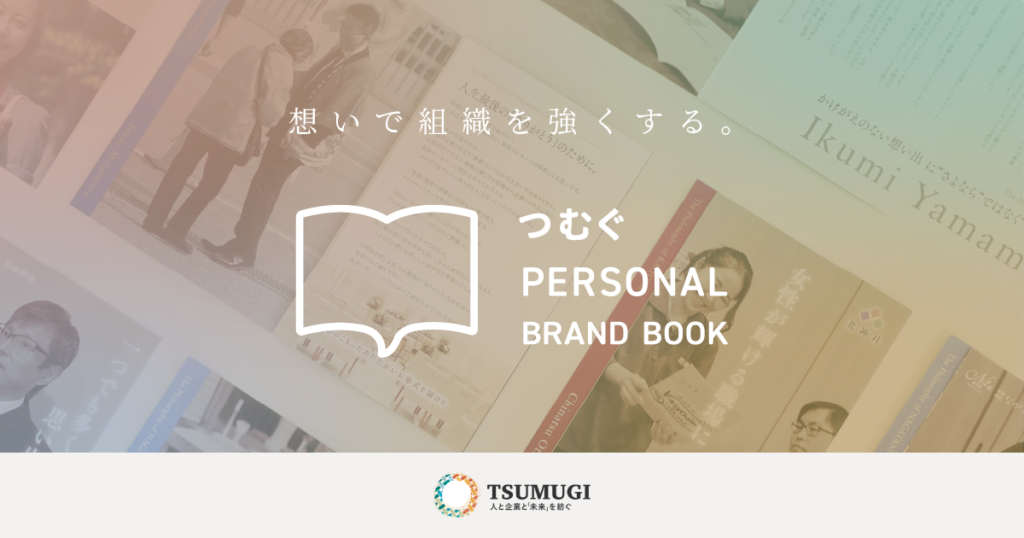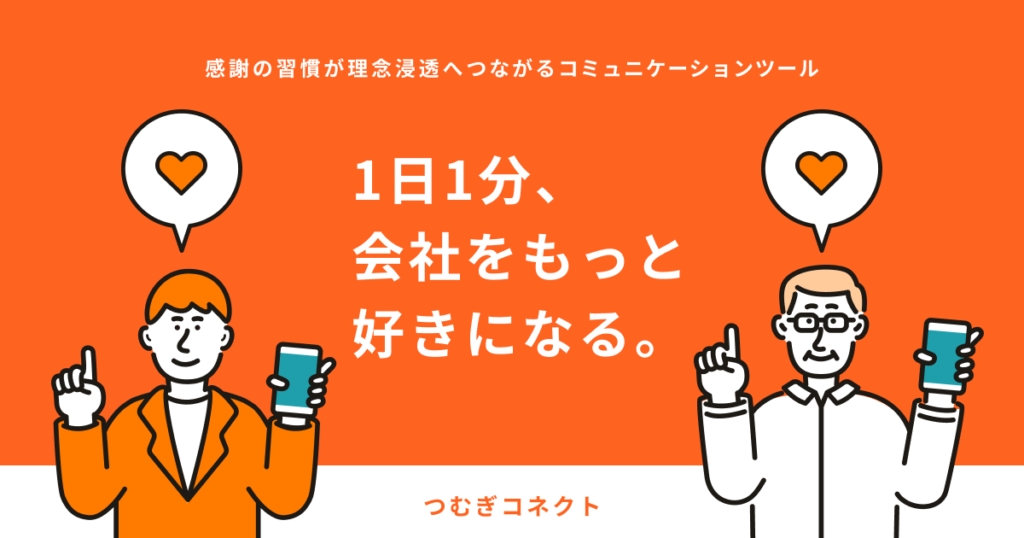株式会社武蔵屋様の概要
株式会社武蔵屋様は山形県で葬祭業・仏壇店・墓石業と、お悔やみに関わる様々なお手伝いをしている企業です。仏壇販売から企業の歴史をスタートさせ、その後、墓石や葬祭といった分野へ事業を拡大されてきました。創業から130年以上の歴史を持ち、葬祭ホールや墓石のショールームを含め13の施設を運営しています。
支援の背景
VMVリブランディングについてご相談をくださったのは現社長の息子様・柘植大輔様でした。
つむぎでは以前に柘植様にインタビューをさせていただいたことがありましたが、当時はなかなかその想いも表現できず、そのインタビュー内容が形になることはありませんでした。
しかし時が経ち2024年の夏頃、柘植様よりご連絡を頂いたのです。ご連絡の内容は「ビジョン・ミッション・バリューを新しくしたい」というものでした。
多くの後継者は先代から会社を引き継ぐ際に、VMVの刷新を試みます。その会社の経営を引き継いだものとして自身が持つ志、そしてこれからこの会社がどこに進んでいくのかをメンバーに示す必要があるからです。
これまで承継のタイミングでVMVの刷新のお手伝いをさせていただいいたお客様も多くいらっしゃいました。
そうしたお客様と同様に柘植様も、承継にあたって自身の志を示すべく、新たなVMVを形にしたいと考えられていたのです。
実施した施策 ステップ1
VMVリブランディングはお客様のご要望に合わせ、経営者や次期経営者のみで行うか、幹部陣を巻き込んで行うかを決めていきます。
それぞれメリット・デメリットが存在し、例えば経営者や次期経営者のみで進めていくことのメリットにはスピーディーにプロジェクトを進行させられることが挙げられます。
一方でデメリットとして、新たなVMVに反映されるのは経営者や次期経営者の考えのみとなってしまう点です。この場合、社員の納得を得られないといったケースが考えられ、エンゲージメントの低下や離職、最悪の場合、組織崩壊に繋がってしまう恐れがあります。
そのため経営者や次期経営者のみでVMVリブランディング行うといった選択は、比較的規模が小さく、普段から密にコミュニケーションが取れている企業様に適しています。
幹部陣を巻き込むことのメリット・デメリットは今お伝えした事柄の裏返しです。
武蔵屋様は多くの施設を運営されており、社員の数も多い。何より柘植様の希望もあったため、武蔵屋様のVMVリブランディングは幹部陣を巻き込んで進めていきました。
VMVリブランディングは大きく分けて2つのステップで進行します。
ステップ1は「探索ステップ」です。1ヶ月かけ、自社の歴史を整理したり関係者へリサーチをしたりして自社の魅力、強みなどを調査していきます。リサーチで大切なのは過去・現在・未来や、内側・外側といった構造を意識することです。
新たなVMVといっても、これまでと全く別の方向性を打ち出してしまってはいけません。積み重ねてきた自社独自の強みや魅力。それを踏襲しアップデートすることに、VMVリブランディングの本質があります。
具体的には過去を知るために古参社員やOBへのインタビューを、現在や未来を知るために全社員へアンケートを、さらに外側から見た自社を知るためにお客様・取引先へアンケートも行いました。
実施した施策 ステップ2
その後、ステップ2へと移行します。ステップ2は「創出ステップ」で、ステップ1で得られた情報を参考にしながら、新たなVMVを形にしていきます。
創出ステップの最初に行うのは「なぜ私たちはこの事業を行っているのか?」というWHYの理解。今回は参加メンバーによって「武蔵屋にとっての供養とは?」という問いが深められ、新たなVMVの土台となっていきました。
その後キーセンテンスの抽出と構造化、チャンクアップ・チャンクダウン、そして重要キーワードの抽出といったワークを実施しています。
武蔵様の場合では、キーセンテンスが「顧客第一主義」とまとまり、その言葉をチャンクアップ・チャンクダウンして、いくつかのキーワードへ整理していきました。
それらのキーワードと、ステップ1で行った探索ステップで得られたキーワードと組み合わせ、新たなVMVとするべく磨き込みをしていったのです。
プロジェクトの成果
最終的に「日本一の幸せと活力が溢れる社会を創る」というビジョンと、3つのミッション、4つのバリューが言語化されました。
また柘植様からは「みんなと新たなVMV作れてよかった。本当にいいものができた」とご満足の声をいただいています。
出来上がったVMVは、柘植様と社員一人ひとり面談で共有されるとのことです。
またVMVリブランディングを経て深められた考えを他の社員へ伝えるため、動画を制作しているところです。
新たなVMVは本当にできたばかりです。ここからは浸透のための取り組みを進めていく必要があるでしょう。
プロジェクトのポイント
今回のポイントとして挙げられるのは、社員参加型のアプローチをとったことです。
加えてワークをファシリテートする者として、参加者全員の意見を聞き、考えを引き出し、深め、まとめていくことを意識しました。
例えば、Whyの理解のなかで「供養」についての理解を深める場面がありました。
供養とは葬儀の中では、必ず行われなければならないことです。
そのため日常業務の中で、立ち止まってその意味を考える機会はとりづらい。しかし一連のワークを経た今、柘植様と幹部の方々それぞれに「供養とは?」と質問した場合、同じ言葉が返ってくるでしょう。
このような共通言語ができたということは、会社にとって大きな意味があります。
今後の展望
良いVMVには3つのポイントがあると考えています。
1つは「近未来すぎないこと」。2つめは「ワクワクできるか」ということ。そして最後は「社会に貢献できるようなもの」であることです。
1つめと2つめのポイントはVMVを正しく機能させるためのものです。
VMVとは、会社がこれら向かう方向性や将来像、叶えたい世界を言語化したものです。そしてVMVを叶えるべく、経営者含め会社のメンバーは日々に業務に当たります。
そのVMVが例えば明日叶うものだった場合、会社のメンバーはおそらく一生懸命仕事にあたらないでしょう。また、全くワクワクしないVMVだった場合も同様です。
3つめのポイントである「社会に貢献できるようなもの」というのは、これまでの二つは少し違った観点から重視しています。
マズローの5段階欲求にみられるように、人の「何かを成し遂げたい」という欲求は深めれば深めるほど、抽象的に、そして社会的に変化していきます。そのため、もし具体的で自己を中心としたVMVとなってしまった場合、それはまだまだ深く考える余地があることを意味するのです。
武蔵屋様で行ったVMVリブランディングも、もちろんこのポイントを意識しています。
ただVMVは掲げるだけでは意味をなしません。社員それぞれが言葉に込められた想いを知り、理解してはじめて行動につながるからです。
今後は新たなVMVを通し、武蔵屋様がより良い会社となるよう、お手伝いをしていきたいと思います。
つむぎコンサルタント:つむぎ株式会社 代表取締役 前田亮
1981年静岡県生まれ。2004年、慶應義塾大学卒業後、㈱船井総合研究所に入社。社内で初めてエンディング業界のコンサルティングに本格的に携わり、チーム、グループを立ち上げ、2017年から部長として組織マネジメントに携わる。2020年、人創り・組織創りの経験を活かした人材サービスを提供するつむぎ㈱を設立。お客様、社員に愛され、地域になくてはならない永続企業創りを人材戦略の面からサポートする。