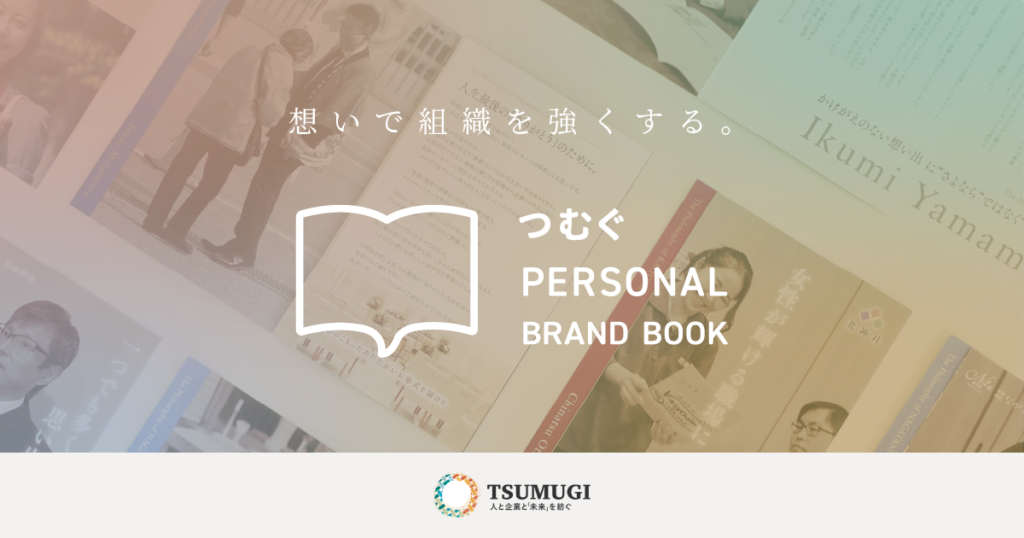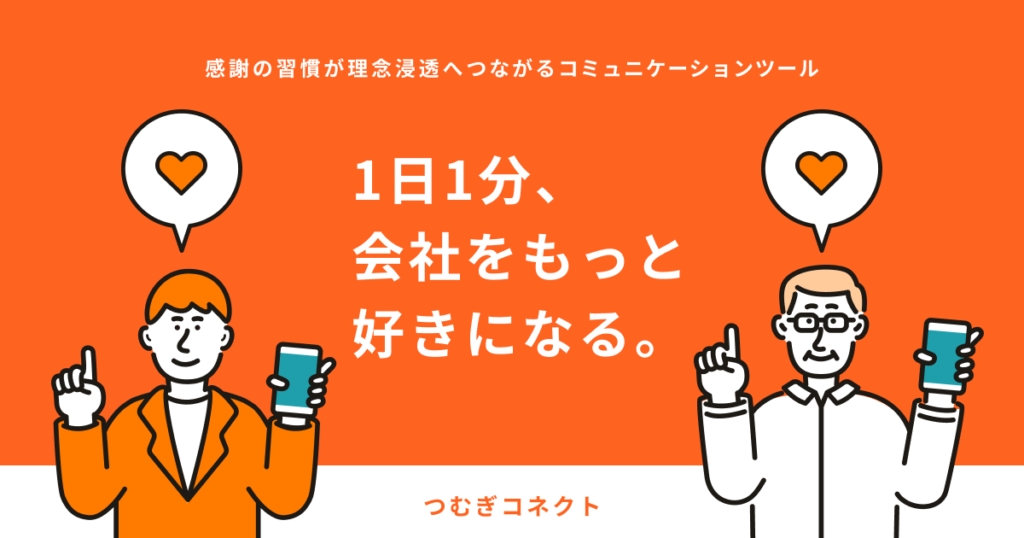新卒採用が難しい産廃業界こそ、戦略的な取り組みが求められています。
産業廃棄物処理業界は、慢性的な人手不足という課題を抱えており、特に新卒採用の難易度は他業界と比べても高いのが現状です。
しかし、新卒人材の採用は、企業文化の継承、組織の若返り、将来の幹部候補の育成といった観点から見ても、重要な経営課題の一つです。
とはいえ、「業界の知名度が低い」「仕事内容の説明が難しい」「そもそも学生からの応募が来ない」といった悩みを抱える中小企業は少なくありません。
結果として、「何から手をつければよいかわからない」と感じている企業も多いのではないでしょうか。
本記事では、産廃業界における新卒採用の現状とその意義を改めて整理するとともに、成功企業の取り組み事例や、明日から実践できる採用戦略のポイントをご紹介します。
「学生に届かない」「何を伝えればいいか分からない」新卒採用が進まない理由とは?
産業廃棄物業界において、新卒採用は今なお大きなハードルとなっています。まず最大の壁は「認知度の低さ」です。学生が業界そのものを知らず、企業名で検索されることもエントリーされることもほとんどないというのが実情です。
また、「3K」といった過去のイメージが根強く残っており、仕事内容を魅力的に伝えることが難しいという声も多く聞かれます。収集運搬や処理といった業務内容は、学生にとってなじみがなく、やりがいや社会的意義が伝わりにくいのが現実です。
さらに、多くの中小企業では中途採用と同じ手法で新卒採用に取り組んでおり、学生向けに特化した説明やインターンシップの設計が不十分になりがちです。「どう話せばいいか分からない」「何を見せればいいか迷う」といった担当者の声も少なくありません。
インターンや説明会を実施しようとしても、企画や運営のノウハウがなく、思うように進まない──そんな悩みを抱える企業も多いのが、産廃業界の現状です。
「ゴミの様子」
だから今、産廃業界に“新卒人材”が必要な3つの理由
こうした課題がある一方で、実は産廃業界こそ「新卒採用」に取り組むべき理由がいくつもあります。
1つ目は、「長期的な人材投資としてのコストパフォーマンス」です。即戦力を求めた中途採用は、採用単価が高く、定着も不安定なケースが多く見られます。それに対して、新卒採用は初期教育の手間はあるものの、自社の文化や価値観を一から伝えることができ、将来的には幹部候補として長く活躍してもらえる可能性があります。
2つ目の理由は、「事業継続と組織基盤の強化」です。新卒社員を多能工として育成することで、属人化の解消や部門間の連携がしやすくなります。特に現場主義の強い産廃業界では、将来を見据えた“育てる人材戦略”が組織の安定につながります。
3つ目は、「新しい価値観やスキルの導入」です。SNSやデジタルスキル、サステナビリティに対する感度など、若い世代ならではの視点は、業界のブランディングや業務改善にも大きな刺激を与えます。これらの新しい力を受け入れることで、組織に変化と柔軟性が生まれます。

「この会社で働きたい」と思わせる“伝え方”と“見せ方”の工夫
新卒採用で成功するためには、「ただ会社の説明をする」のではなく、「自社の魅力、夢を共感できる形で伝える」ことが重要です。
まず、産廃業界が担っている「社会的意義」や「自社の存在する意義」を丁寧に伝えることが基本です。環境保全や都市インフラの維持といった大きなテーマに直結していることを具体的に説明することで、「人の役に立つ仕事をしたい」と考えている学生の共感を得やすくなります。
次に、実際に働く社員の声や成長ストーリーを紹介しましょう。文章だけでなく、インタビュー形式や動画で可視化すると、リアリティが生まれます。「自分と年齢が近い先輩が、どうやって仕事に慣れたのか」「どんなやりがいを感じているのか」といった具体例は、応募の後押しになります。
また、「安心して成長できる職場環境」を数値と事例で示すことも効果的です。たとえば、教育制度の内容、資格取得支援、福利厚生の制度などは、入社後の安心感につながります。
さらに、現場の雰囲気が伝わる写真や動画も積極的に活用しましょう。無理にカッコよく見せる必要はありません。「現場で働く人の表情」や「チームで動いている様子」など、リアルな姿を見せることで、“自分が働くイメージ”を持ってもらいやすくなります。
「まず何から始めればいい?」新卒採用の進め方5ステップ
新卒採用の取り組みは、一気にすべてを完璧に整える必要はありません。以下の5つのステップで段階的に進めることで、着実に成果につながっていきます。
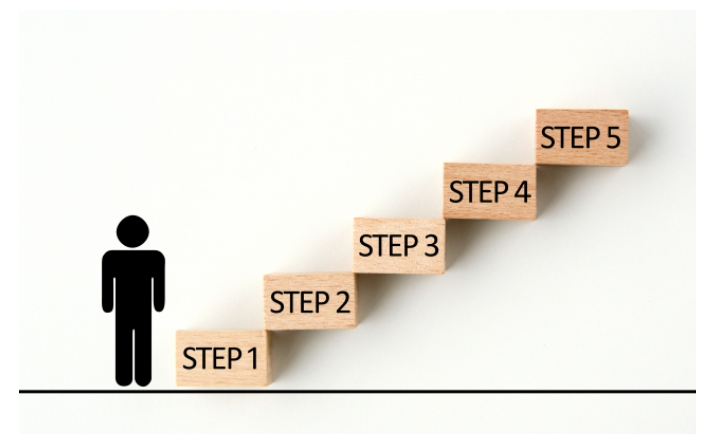
Step1|採用ターゲットの明確化
まずは、「どんな人に来てほしいのか」を明確にします。文系理系問わず幅広く受け入れるのか、地域志向の強い学生を求めるのか──自社の働き方や育成体制に合った人物像を整理しておきましょう。
Step2|採用資料・会社説明資料の準備
新卒向けに理念や事業内容、職場環境などを伝える資料を用意します。特に業界未経験の学生にとっては、「この会社で働くことのイメージ」ができることが重要です。現場の写真や社員インタビューを盛り込むと、より伝わりやすくなります。
Step3|学校訪問、合同説明会、Web活用など接点の最大化
採用広報の基本は「知ってもらうこと」です。高校や専門学校への訪問、大学主催の合同説明会への参加、Web説明会の実施など、学生との接点を少しでも多くつくることが大切です。
Step4|インターン・見学会の実施
インターンや見学会は、「働くイメージ」を具体化するための最も効果的な場です。実際の作業現場を見せたり、先輩社員と話す機会を設けたりすることで、「ここで働いてみたい」という気持ちを引き出すことができます。
Step5|選考〜内定フォローの丁寧さで「辞退率」を防ぐ
最後に重要なのが、選考中や内定後のフォローです。選考の過程でも一人ひとりに丁寧に向き合うことで、信頼が生まれます。内定後は、職場見学や先輩との座談会などを通じて「入社後の不安」を解消する機会をつくり、辞退率を下げていきましょう。
「本当に応募はあるの?」「人手が足りない……」新卒採用の現場でよくある疑問に答えます
Q. 学生は産廃業界に本当に興味を持ってくれる?
A. 社会貢献性や安定性を伝えることで、共感する学生は確実にいます。
Q. 採用専任者がいなくても可能?
A. 経営者や現場リーダーが“顔を出す”だけでも信頼されます。小規模説明会も有効です。
Q. 地方企業でも都市部の学生に来てもらえる?
A. 寮・交通費補助・UIターン支援などがあれば可能です。また、地方の暮らしや働きやすさを伝える発信も効果的です。
「何から整えればいい?」と思ったら 30分無料相談と事例紹介はこちら
もし「どこから手をつけていいかわからない」「どんなが考え方が必要なのか?」と感じられた場合は、ぜひお問い合わせをいただければと思います。中小企業の人事領域に対し豊富な知見を持つコンサルタントと、30分間無料でご相談が可能です。
つむぎではこれまで多くの中小企業様に採用支援をご提供してまいりました。新卒支援に関する成功事例をまとめた記事がございますので、ぜひご参考にしてください。
新卒採用に関係する記事は下記にもまとめています。この機会にぜひご一読ください。
8月4日には産廃業界に特化した採用戦略、そしてその成功事例を紹介する無料のオンラインセミナーを開催いたします。ゲストは東京都八王子市で活躍するまごころ清掃社様です。時間は10時から。ぜひご参加ください。
“人が育つ会社”が生き残る──新卒採用が、未来の組織を変える

採用難の時代に「自社で人を育てる」ことは、最大の経営戦略です。
産業廃棄物業界は、環境や地域の未来を支える重要な産業です。
その価値を、次世代にどう届けるか──。
新卒採用の一歩が、企業の未来を変える第一歩になります。